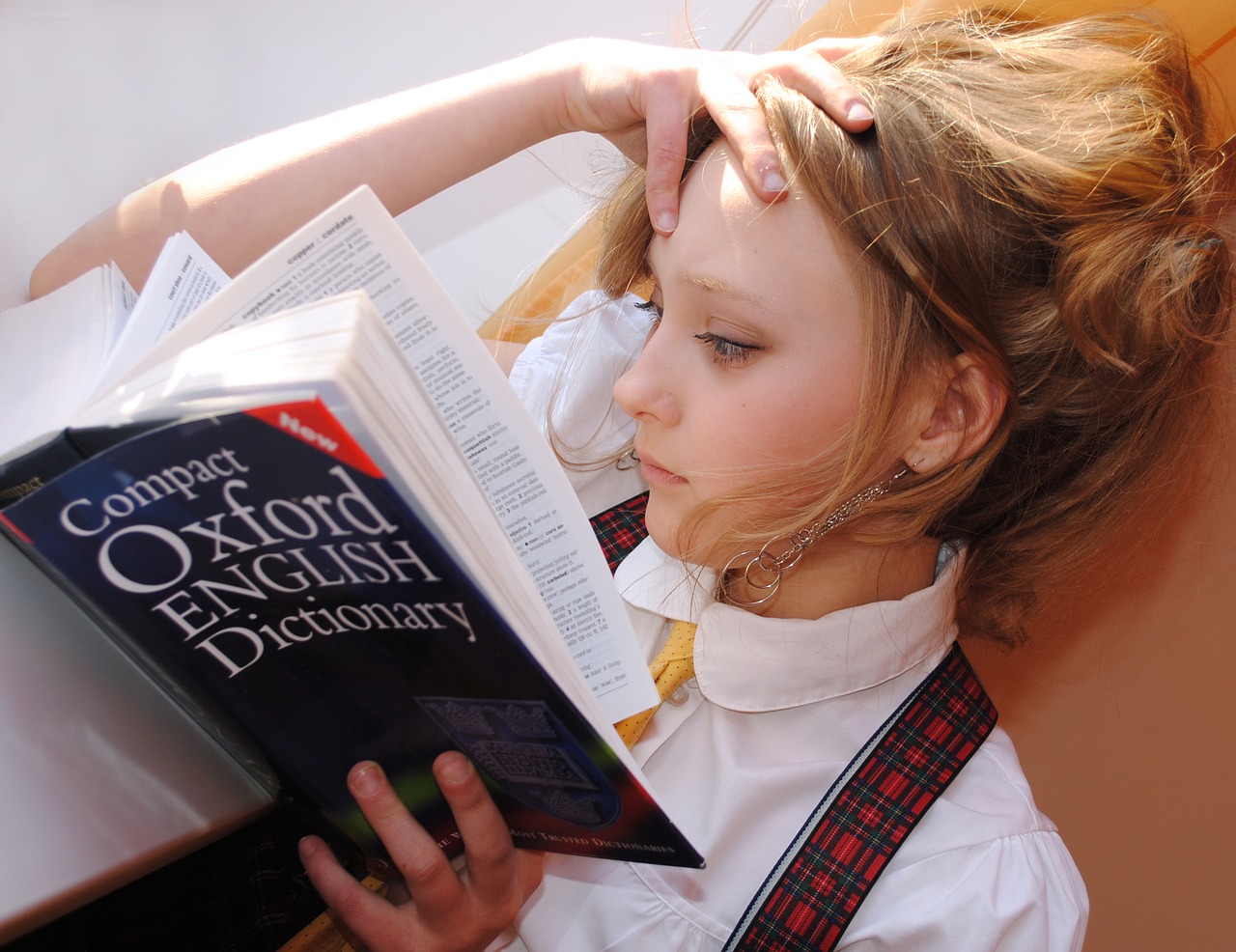『読解力』とは、物事を正確に理解する力。
文章の内容を正確に読み取ったり、
会話で相手の話しの意図を理解するなど、
あらゆるシーンで必要なスキルですよね。
なのに・・・・・、読解力のない日本人が増えているというのです。
特に今の若年層は、かなり読解力が落ちていると・・・・・。
教科書が読めないという高校生も、たくさんいるというから驚きです。
これって、子供の問題として取り上げられているけど、実は大人こそ必要なスキルなんですよ。
読解力は勉強のためだけでなく、人が豊かに生きていくために必要な、判断力や思考力のベースにもなるものです。
子供の問題として取り上げられていますが、実際には大人こそ必要なスキルなのです。
今回は、大人の読解力の重要性や能力を高める方法をお話ししていきましょう。
OECD調査における日本の読解力ランクが下落している

OECD(経済協力開発機構)は学習到達度調査(PISA)として、義務教育修了段階の15歳児を対象に2000年から3年ごとに実施されるものです。
いわゆる国際学力調査といわれるもので、読解力・数学的リテラシー・科学的リテラシーの3分野を対象としています。
2019年12月公表された結果によると、
日本の読解力は15位で前回調査時の8位から大幅に順位を落とし、読解力の低下が問題視されています。
文部科学省の「読解力」向上に関する指導資料[参考資料:読解力向上プログラム]
現代で求められている読解力とは、
●テキストを読み解く能力
●自分の意見を論じるスキル
●文章以外の図やグラフなどの情報を読み解く能力
なども含まれています。
今!世の中に読解力のない人が多すぎる

SNSが発達したおかげで、手軽にリアル情報を手にすることができるようになった一方で、
Twitterの炎上が多く見られるようになりました。
Twitterで炎上する原因は、言葉の発信に責任感が足りない人が多いからですが、どうやら「読解してない」ことも原因のひとつのようです。
つまり何を言っているのか、真意を分かっていないワケです。
文脈も行間も読めてない。
最近は、漫画が読めないっていう人もいるとか・・・・・。
漫画と言えば、『ドラゴン桜』でも、読解力を取り上げていましたよね。
ドラゴン桜は2003年に講談社の「モーニング」という雑誌で連載されていた漫画です。
一躍ブームとなり「講談社漫画賞」や「文化庁メディア芸術祭漫画部門優秀賞」を受賞し、2005年にはドラマ化されました。(平均視聴率が16.2%の大ヒット)
2018年からは、その続編となる『ドラゴン桜2』の連載が開始になり、2020年度以降の大学入試改革に焦点をあてた新シリーズです。
学び方を学べ!ドラゴン桜公式マガジン(noto)
下記は、「ドラゴン桜2」公式マガジンのキャッチフレーズ。
社会はいま、大きく変化している。
そんな時代に求められているのは何だ?
知識そのものなんかじゃない。
知識を「活かす力」だ。
・・・・・・・・・
自分をアップデートできる人間になれ!
今の漫画は、バカに出来ないよね~。
社会人の学びに有益な情報もあるので、私もブログを書き始める前に改めて読んでみました。
今からでも遅くない!大人の学びの良い刺激になること間違いなしの漫画です。
考えさせられることが多いので、読んでない人は、ぜひ一読を!
読解力については【第6巻:読解力の身に付け方】
なぜこれほど、読解力が重視されるのでしょうか?
学歴や職業や年収は読解力が左右する
格差社会の根っこにあるのは、個々の基本的な読解力(=国語力)が判断力や思考力に左右するからです。
読解力は、論理的思考力がなければ言葉や文章は理解できません。
つまり、「自分の頭で考える」ことが必要です。
さらに大人の読解力には、論理的思考力と鋭敏な感性が必要になってきます。
そもそも人間関係におけるトラブルの多くは、相手が「何を伝えたいか」「何を言いたいか」を正しく理解できていないことから発生するものです。
相手の真意や心情を正確に読み取ったり、状況や場の空気を把握する『感情を読み取るスキル』まで要求されることがほとんどです。
だから社会に出れば、コミュニケーション全般にも関わってくる読解力と、論理的思考力の差が表に出てくるワケです。
自分の読解力を知らない人や、読解力に自信がないという人は、読解力テストを受けてみるのがおすすめです。
読解力テストにチャレンジしてみよう!
まずは、これから
▶Literas(リテラス)論理言語力検定 公式サイト(例題を無料で見ることができる!)
語彙力だけでなく、様々な理解力を含めた総合的な言語能力を測定することができる検定です。
【その他の読解力を試せるサイト】
▶第3部 読解部門 | サンプル問題 | BJTビジネス日本語能力テスト
▶読解力テスト|国語の中学受験対策なら家庭教師の「リソー教育システム」
では、ここからは読解力を高める方法をお伝えしますね。
書くことが重要!読んで書くから読解力が自分のものになる

読解力を高めるには、たくさんの本を読むと良いとか言われているので、大人でもたくさん読めばいいと思っています。
でも、読解力は、読書量に比例するとは限らないのです。
本を読まない人や国語が苦手だった人は「たくさん読んではいけない」
読解力がないうえに量を読むと、ただの流し読みだけで終わってしまうので逆効果。
では、どうすればいいのか?
たくさんの本を読まなくていいので、1冊を何度も読んで本に書いてあることを評論しましょう。
自分だったらどう考えるのか
自分だったらどう行動するのか
と自分に置き換えていく読み方をするのです 。
一般的に本というのは、1冊から重要な情報が1つか、ためになることが1つ得られたら読んだ価値があると言われています。
大切だと思うことは3つ以内に絞り、それを試しにやってみるということをするのです。
そうすると読解力だけでなく、行動力もついてきます。
本が好きではない人が、本を読んで読解力を高める方法は、量ではなく「精読」だということがポイントです。
では、ビジネスにおける読解力を付けるには、どうすればいいのでしょう。
ビジネスにおける読解力は「要点を探す力」
核心の部分を探していく読み方のポイントは、1ページに1つのアンダーラインだけに絞る読み方をします。
見つからなくてもいいので、とにかく必要のない部分を捨てる読み方をしていきます。
重要な部分だけを抜き出し、頭の中で混ぜ合せて考えることで、本に書かれた知識以上に、自分で考える力がついてきます。
たくさんのラインを引きすぎると、分解して考えることができなくなるので、ただの読書に終わらないようにしましょう。
次に読解力をつけるうえで、最も重要なのが文章を書くことです。
書くことができない人は読むこともできない
読解力を自分のものにするには、読むだけでは力がつくはずがありません。
最終的に書くからこそ、正確に読み取れるようになるのです。
例えれば、テニスを習得するのに実際にプレイしないまま、テニスのやり方を習っているのと同じこと。
文章を書くことと読むことは、表と裏の関係です。
このブログでは書く力を付けることをすすめている理由は、どんな能力も自分の力として定着させるのに最強の訓練方法でもあるからです。
読解力も思考力も、自分のものにするのであれば、読む⇒要約する⇒書くを習慣化するまで繰り返すことです。
読解力は大人こそ必要なスキル

読解力は勉強のためだけでなく、人が豊かに生きていくために必要な、判断力や思考力のベースにもなります。
大人の読解力とは言葉や文章を正確に判断すると同時に、
●人の心の在り方や感情を理解する力
●状況や場の空気を把握する力
といった感情理解のスキルも必要になります。
会話読解力があれば、相手が言った言葉の真意を理解することができ、相手の気持ちを察することができます。
しいては、コミュニケーション能力に繋がってもいくのです。
感情理解のスキルを高めるには、どうすればいいのでしょうか?
小説は感情の読解力の向上に繋がる
小説には様々な人物の欲望、嫉妬、愛、憎悪といった人間の本質や、人生観や価値観などが描き出されています
●自分自身の価値観と小説を比べて読む。
●登場人物を周囲の人に置き換える。
●登場人物の感情を推察し心理や行動を想像する
など、
同じ世界を疑似的に生きる読み方を積み重ねることで、
リアル世界の人間関係においても相手の考えや気持ちを察する力が身についてきます。
大人だからこそ絵本を読もう!

絵本には、ビジネス書や実用書にはない思考力や想像力を向上させる効果があるので、読解力を高めるにも役立ちます。
絵本は、自分で考え・想像することで、新たな真実や気付きを手に入れることができます。
また、脳科学によると、絵本のページをめくるという行為には、右脳の視覚的な記憶力を育てる働きがあるのだそうです。
絵本のページをめくる際、脳は直前に見た映像記憶を頭に残しながらストーリーを追っています。
この機能はスケッチパッドファンクションといわれていて、この機能を働かせながら絵本を読むことは脳トレになるのだそうです。
今の大人はスマホや携帯で、漫画や本を読んでいる人が多くいます。
でもそれは、字を読んだついでに絵を見て理解している状態なので、あまり脳の刺激にはなっていないのだそうです。
脳への刺激は、 絵を見て記憶力と想像力を働かせた上で、字を読むとより効果があるので絵本がピッタリなんですね。
だから、子どもよりも大人の方が、絵本を読むべきだと言われています。
日本の絵本界を代表する作家ともいわれる絵本作家:五味太郎氏が言うには、
“つくづく絵本は、ガキにはもったいないと思う”。
絵本には「何歳向けの絵本」などというものは存在せず、年齢に応じて何を感じ取るかが絵本のすべてである。
と・・・・・・そんなこと言われたら、大人も読んでみたくなりますよね!
絵本の魅力は「全てを語り切っていないところ」でもあり、余計な言葉が削ぎ落とされることで本質が伝わるところです。
大人になってからの絵本・・・・・今の自分が何を感じるかを確かめてみるのもひとつなのでは・・・・・・。
脳を知ると能力は伸びる!年齢に関係なく脳は成長している

脳科学での人間の脳は、思想や気持ち・置かれた環境など、あらゆる状況に適応しようとして形を変えていくといいます。
だから苦手意識や「できない」と思った瞬間、脳は働かなくてもいいと判断してしまうのです。
「自分はスゴイ!」「やればできる!」と思っていたら、それを実現できる能力を脳が作っていきます。
「得意じゃないから」とか「今さら自分の性格は変えられないから」と思うこと自体が、脳の成長を止めているのです。
年齢に関係なく、人の脳はすべて成長途中にあります。
逆に今、高い能力を持っていても、継続的に育てなければ能力は伸びていきません。
変化を求められる時代に、中高年にも社会人基礎力が必要であり、またそれは「学び続ける」ことによって身につけることができるとされています。
そのうえで年齢を重ねても、自分に欠けているものをどう自覚して、
どのように能力を身につけていくのかを一人ひとりが考えることが大事になってきます。
厚生労働省の能力開発基本調査によれば、
1年間で10時間未満の学習をしている層を除けば、能力開発などの自己啓発を行っている人の割合は24%。
その他、本を読まない人が相当数いるようです。
いったい日本の大人たちの1日の平均学習時間は、どれくらいなのでしょうか?
実は、総務省統計局が出したデータがあります。
1日平均=6分
実際には、一部の人は毎日読書やその他の学習をしているけど、自ら進んで何かを学ぶ時間をつくっている人は少ないということなのでしょう。
※年収500万円台の方と2,000万円以上の方の平日の学習時間に関する調査
言葉を使い、文章を書き、読解力を高めることで、仕事以外にもコミュニケーション能力や暮らしの質も高まります。
まずは、明日からでもすぐに実践できることから学びを始めてみましょう。